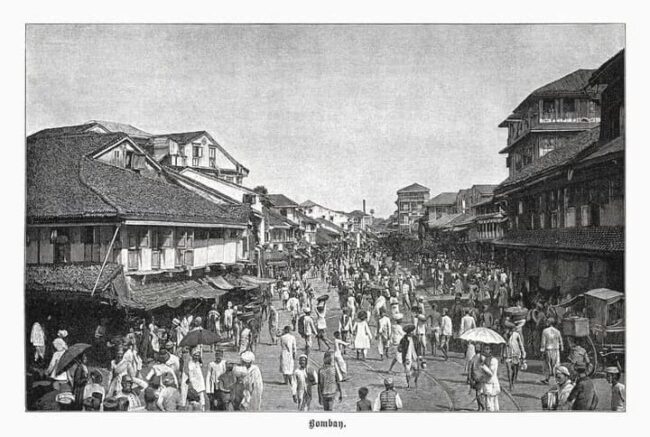印パのむなしい停戦…インド・パキスタンどちらの政府でもない「本当の敗者」とは?


インド北部の「虐殺」が全面「核戦争」に発展するかも…日本人が知らない印パ間の深すぎる「確執」

インド各地では、22日に発生したテロ事件に対する抗議が行われている
<カシミール地方で起こったテロで印パ関係が急速に悪化。事態がここまで悪化した背景には、長きにわたる、想像以上に根深い確執があった>
インド北部で起こった「虐殺」が核保有国同士の全面戦争に発展するかもしれない。
4月22日、イスラム過激派が、インドが実効支配する係争地ジャム・カシミール州の丘陵地帯の町パハルガムで、ヒンドゥー教巡礼者や観光客に向けて発砲、26人が死亡した。その後、パキスタン関連とされる武装勢力ラシュカレ・トイバの分派組織である「抵抗戦線」が犯行声明を発出した。
インド政府はこの攻撃についてパキスタンの責任を指摘し、「越境テロ」と非難。両国間の主要な陸路国境を閉鎖し、パキスタン人に対するビザ発給を停止、さらに外交官を除くすべてのパキスタン国民にインドからの国外退去を命じるなどの措置を講じた。
インドのナレンドラ・モディ首相は、今回のテロ事件の首謀者に対し「地の果てまで追い詰めて罰する」と宣言した。
一方、パキスタン側は関与を否定。同国のカワジャ・アーシフ国防相は英スカイニュースの取材に対し、インドが「偽旗作戦」で今回のテロ事件を「自作自演」したと主張した。
アーシフはインタビューで「インドによるいかなる行動にも、われわれはそれに応じた対応を取る」とインドに警告した。「もし全面攻撃などがあれば、当然全面戦争となるだろう。事態が悪化すれば、この対立は悲劇的な結果を招きかねない」
加えて、アーシフは世界、中でも「世界の大国を率いる存在」であるドナルド・トランプ米大統領に対し、事態を「理性的に収拾させる」よう介入を求めた。インドとパキスタンは両国とも核兵器を保有しているからだ。
「アメリカが介入しなければ、インドが動いた際、われわれも同様の行動をとらざるを得なくなる」
インドのラジナート・シン国防相は、23日の「空軍元帥追悼式」で「この事件の実行犯だけでなく、その背後でこのような邪悪な行為を首謀した者たちにも責任を取らせる。首謀者には、近いうちに相応の報復が待っている」と語った。
英王立防衛安全保障研究所(RUSI)の准研究員であり、キングス・カレッジ・ロンドンの上級講師でもあるウォルター・ラドウィグは本誌に対し、「両国ともに核兵器を保有している。核保有国同士が衝突するとなれば、事態は深刻だ。われわれはこの問題を懸念すべきだ」と語った。
そして、両国の核戦力を管轄する高官たちは有能だが、「何かの拍子に誤解をしてしまう可能性は常にある」とラドウィグは付け加えた。
フセイン・ハッカニ元駐米パキスタン大使は本誌に対し、「現時点でインドは外交的な対応に留めているが、いずれ懲罰的な行動に出る可能性が高い」と懸念を示した上で「インドの報復行為や、それに対するパキスタンの報復によって緊張が高まる可能性はある。しかし、核兵器を保有する国同士の全面戦争を望む者はいないだろう」とした。
そして、「現在の大きな問題は、両国を戦争寸前の状態から引き戻すための十分な関与をアメリカなどの強国がしていないことだ」とアメリカなどの国を批判した。
キングス・カレッジ・ロンドンのインド研究所のスリナート・ラガバン上級研究員はBBCに対して、「インドの国内世論やパキスタンに向け、インド政府は決意を示す強力な対応をするだろう」との予測を語った。
そして、「2016年以降、特に2019年からは、報復の基準は越境攻撃または空爆に設定されてきた。今さらそれより手緩い対応で済ませることは困難だ。パキスタンも報復に出るだろう」との見通しを示した。「インドとパキスタン、それぞれに見通しを誤るというリスクが常に付きまとっている」
ラガバンの挙げた2016年と2019年にはカシミールで両国間の衝突が起こっている。
2016年、インドはパキスタン支配地域にあるとされる武装勢力の発射拠点を攻撃した。これは、カシミールのウリ地区で29人のインド兵が殺害された事件に対する報復だった。
2019年には、インドはパキスタンのバラコットにあるとされる武装勢力の訓練キャンプへの空爆を実施した。これは、カシミールのパルワマ地区で少なくとも40人の準軍事部隊員が殺害されたことへの報復だった。
インドとパキスタンは、1947年の独立以来、カシミール地方を巡って対立を続けてきた。両国ともカシミール全域の領有権を主張しているが、実際には異なる地域をそれぞれ支配している。
この領有権争いは、1947年、1965年、1999年の三度にわたる戦争と、数多くの小規模な衝突、そして現在も続く国境での緊張を引き起こしてきた。
数十年にわたり、インド支配地域では分離独立を求める武装反乱も発生し、数万人が命を落とした。
パキスタンはカシミール人の「自決権」を支持していると主張する一方、インドはパキスタンが武装勢力を支援して越境攻撃を行わせていると非難している。パキスタンはこれを否定している。
現在、インド支配地域とパキスタン支配地域を分断する「管理ライン」は、両国側とも重武装化されている。